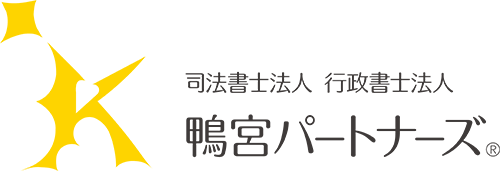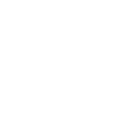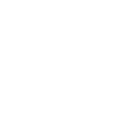一般的に30~40代を迎えると、ご両親が高齢を迎えているご家庭が多くなります。
まだまだご健在なうちは良いのですが、場合によっては「生前対策」「相続対策」といった事を考える必要があるかもしれません。
ご実家の不動産やある程度の預貯金、株式などをお持ちの方にとっては、「生前対策≒税金対策」という方も多いのではないでしょうか??
財産の移転に関する制度を大別すると、「生前贈与」と「相続」という方法があります。
生前贈与は、人が生きている間に自分の財産を他人に贈与することを指し、一方で相続は、人が亡くなった後にその財産が法定相続人に移転することを指します。
この記事では、生前贈与と相続の違い、それぞれのメリット・デメリット、そしてどちらがを選択するべきなのか??について解説します。
1.はじめに
生前贈与と相続、どちらが有利なのか結論を先に述べてしまいますと、「ご家庭の資産状況によってケースバイケース」となります。
「そんなの当り前じゃないか!!」とお叱りの声が聞こえてきそうですが、これには理由があります。
- 資産額がどれくらいか
- 基礎控除額がいくらか
- 家族構成はどのようになっているか
- 各種特例の利用が可能か
上記に挙げた要因によって、生前贈与をするべきか、相続で財産承継するべきかの判断基準が異なってきます。
また、対策したい内容が、そもそも「税金」なのか、「承継先」なのかでも異なります。
次の章より、生前贈与と相続について比較検討していきましょう。
(本投稿の内容は2023年5月時点の情報を基にしています)
2.生前贈与と相続の概要

生前贈与とは、人が生きている間に自分の財産を他人に贈与することを指します。
生前贈与は親族間で行われることが多く、親から子への贈与が一般的です。
生前贈与には税金上のメリットがあり、生前贈与を行うことで、後の相続税の節税対策として利用することができます。

一方、相続とは、人が亡くなった後にその財産が法定相続人に移転することを指します。
法定相続人とは、民法に定められた順位に従って相続権を持つ人々のことです。
相続税の節税対策として、遺言書や生命保険等を活用することができます。
生前贈与を行った場合、受贈者は贈与税を納める必要があり、また相続の場合にも、相続人は相続税を納める必要があります。
ただし生前贈与についても相続についても、一定の非課税枠が設けられており、その非課税枠内で収まる部分については基本的に税申告する必要がありません。
2-1.贈与税の特徴
贈与税は、受贈者が受け取った財産の価値に応じて計算されます。
ただし、一定額以下の贈与については非課税枠が設けられており、非課税枠部分については贈与税は課されません。
生前贈与の代表的なものを挙げると、年間110万円までの暦年課税による贈与と、累積2,500万円まで贈与税がかからず相続時に相続税の持ち戻し対象となる相続時精算課税制度があります。
こちらについては今後法改正の対象となっていますので、詳しくは別のトピックスをご参照ください。


非課税枠の額は変動することがありますので、詳しくは国税庁のホームページ等で確認してください。
→国税庁ホームページ【No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)】
2-2.相続税の特徴
相続税は、相続人が受け取った財産の価値に応じて計算されます。
相続についても基礎控除額という非課税枠が設けられています。
現行の制度では、『3,000万円+法定相続人の人数×600万円』という算出方法があり、被相続人(故人)の法定相続人の人数によって基礎控除額は変動します。
【例】父の相続で、相続人が妻と子2人の場合
3,000万+600×3人=4,800万 ←相続財産がこの金額の範囲内であれば相続税は非課税
相続税の計算方法の詳細については下記のトピックスをご参照ください。

相続税の基礎控除額についても変動することがありますので、詳しくは国税庁のホームページ等で確認してください。
2-3.贈与税と相続税の比較

ここで贈与税と相続税について比較検討してみましょう。
<税申告の対象となる人>
- 贈与税:受贈者が受け取った財産の価値に応じて計算される
- 相続税:相続人が受け取った財産の価値に応じてそれぞれ個別に計算される
生前贈与の場合は単純に贈与された人の金額に対して贈与税計算しますが、相続税の場合は最初に故人の財産額から相続税計算した上で、遺産分割の割合によって各相続人が相続税を申告するという流れです。
<申告の時期>
- 贈与税:贈与を受けた年の翌年の2/1~3/15の間
- 相続税:被相続人が亡くなった事を知った日から10ヶ月以内
贈与税と相続税はそれぞれ原則としての申告期限が設けられていますが、その時期は異なります。
また贈与税は明確に期間設定されていますが、相続税については『亡くなった事を知った日から』という少し曖昧な表現となっています。
これは例えば、故人が亡くなった事自体を時間が経過してから知ったというケースや、相続放棄などで、元々相続人ではなかった立場から相続人となったというケースなどの救済措置の意味合いを含むと考えられています。
<非課税枠について>
- 贈与税:1年間に受け取った贈与の合計額に対して適用される
- 相続税:1回の相続において受け取った財産の価値に対して適用される
贈与税と相続税にはそれぞれ非課税枠が設けられており、一定額以下の贈与や相続については非課税となります。
ただし、生前贈与では年間に何回贈与した場合でも、その累積金額について贈与税申告するのに対し、相続では1回の遺産分割(後から未分割の遺産が発見された場合を除く)によって取得した財産についての申告となります。
3.生前贈与と相続のメリット・デメリット

生前贈与と相続には、それぞれにメリット・デメリットがあります。
3-1.生前贈与の場合
メリット
- 節税対策として利用できる
- 贈与者が自分の意思で財産を自由なタイミングで分配することができる
- 相続トラブルを回避することができる
- 相続人以外にも財産を渡すことができる
- 手続きが比較的簡単に出来る
生前贈与をすることで、その分の相続財産を減らすことが出来ます。
暦年贈与等の非課税枠を積極的に利用することで、さらに相続税の圧縮に繋がります。
将来の相続人の関係性が心配なときには、遺留分対策・遺産分割対策としても効果があります。
また相続と比べて、贈与のタイミングや回数、贈与する相手の自由度が高く、当事者間で済むため手続きが比較的簡単にできることも挙がります。
デメリット
- 贈与者が生きている間に財産を手放す必要がある
- 贈与税の他、不動産の登録免許税や不動産取得税の税率が高くなる
- 贈与の時期によって、相続税の持戻し対象となってしまう
生前贈与をすると、当然その分について贈与者の財産が減ることになります。
無計画に贈与をしてしまうことで、その後の贈与者の生活が苦しくなってしまっては本末転倒になってしまうので注意が必要です。
生前贈与をした場合、相続と比べて贈与税の他、登録免許税・不動産取得税(不動産贈与の場合)といった税金の税率が高いという特徴があります。
そのため、支払う側のにもある程度の資力が必要となります。
また、せっかく贈与をしても、贈与者が亡くなってしまった時期によっては、贈与分が相続財産に持戻し対象となってしまうこともあります。
現行制度で暦年課税で贈与した場合は、死亡前3年間分の贈与は持戻し対象です。
2024年からは、法改正により死亡前7年間分までに拡大することが決まっています。
3-2.相続の場合
メリット
- 遺言書や生命保険等を活用することで節税対策ができる
- 様々な相続税の控除が受けられる
- 不動産の場合、贈与と比べ登録免許税・不動産取得税の税率が低い
相続の場合、基本的には亡くなった時点の相続財産を対象に遺産分割することになります。
そのため、生前対策として遺言書や生命保険等を活用することで、相続財産を圧縮し節税することが可能です。
生前贈与と比べて、相続税には様々な控除や特例が用意されています。
こういった税制を活用することで、財産額が高額であっても、結果的に相続税申告する必要がなくなるケースもあります。
相続の場合、生前贈与と比べて不動産の登録免許税の税率が低くなり、不動産取得税に至っては非課税となります。
不動産の評価額は高くなりがちですから、こういった税金が低く抑えられるのは非常にメリットとして大きいでしょう。
デメリット
- 相続人間のトラブルが起こる可能性がある
- 法定相続人以外には相続権がない
- 相続人が相続税を納める必要がある
相続の場合、法定相続人の関係性によってはトラブルのきっかけになってしまうことがあります。
こういった可能性がある場合、遺言書を書くなど早めの生前対策が必要となります。
相続の場合、相続権があるのは民法で定められた法定相続人と決まっています。
かみ砕いていえば、戸籍上の血縁関係がある者となります。
そのため、内縁の妻といった戸籍上では血縁者とならない人には相続権がありません。
また、子が生存している状況では、孫は相続人にすることが出来ません。
故人の財産額によっては、相続人は相続税を納める必要があります。
前もって認識している生前贈与と違い、相続は突発的に発生することが多いため、相続人が突然の相続税に苦しむ、といった状況が発生する可能性があります。
4.生前贈与と相続の有効な特例

生前贈与にも相続にも、それぞれ有効な特例が存在します。
ここでいくつかご紹介しましょう。
4-1.生前贈与の特例
贈与税が非課税となる特例として、次のようなものがあります。
それぞれについて確認してみましょう。
➀住宅取得資金の贈与
令和4年1月1日~令和5年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合、一定の要件を満たすと、贈与税が非課税となります。
非課税限度額は、省エネ等住宅であれば1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円です。
→国税庁ホームページ【No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税】
<要件>
- 贈与を受けた人が受贈者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
- 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)
- 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること
- 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除く)
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること(贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできず、修正申告が必要)
②教育資金の贈与
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から教育資金を贈与された場合、一定の要件を満たすと、贈与税が非課税となります。
非課税限度額は、1人18歳までに1,500万円まで(学校等以外への支出は500万円まで)です。
→国税庁ホームページ【No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税】
<要件>
- 贈与を受けた人が受贈者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
- 教育資金が学校教育費、教育費、介護費用に充てられること
- 教育資金が教育資金の一括贈与契約に基づいて贈与されること
- 教育資金が受贈者名義の預貯金口座に預け入れられること
③夫婦間での居住用不動産の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間で不動産を贈与する場合、一定の要件を満たせば、贈与税を非課税で贈与できる制度です。
非課税限度額は、2,000万円(暦年課税の基礎控除額を除く)です。
→国税庁ホームページ【No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除】
<要件>
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
- 贈与を受けた者が、贈与税の申告書に、当該不動産の所有権移転登記の日付を記載していること
④結婚・子育て資金の贈与
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金を贈与された場合、一定の要件を満たすと、贈与税が非課税となります。
非課税限度額は、1人1,000万円まで(うち結婚関係は300万円まで)です。
→国税庁ホームページ【No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税】
<要件>
- 贈与を受けた人が受贈者の直系卑属(18歳~50歳までの子や孫等)であること
- 結婚・子育て資金が結婚、子育て、介護費用に充てられること
- 結婚・子育て資金が結婚・子育て資金の一括贈与契約に基づいて贈与されること
- 結婚・子育て資金が受贈者名義の預貯金口座に預け入れられること
4-2.相続の特例
相続においても、次のような制度や特例があります。
こちらもそれぞれ確認していきましょう。
➀小規模宅地等の特例
被相続人(亡くなった人)が住んでいた宅地や、被相続人が事業を行っていた宅地について、一定の要件を満たす人が相続した場合に、宅地の評価額を最大80%減額できる特例です。
→国税庁ホームページ【No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)】
<要件>
- 宅地の面積が330㎡以下であること
- 相続人が被相続人と生計を一にする親族であること
- 相続人が宅地を相続した後に、自ら居住または事業を行うこと
②配偶者の税額軽減
配偶者が被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合に、配偶者の相続税額を一定額軽減できる特例です。
配偶者の法定相続分相当額または1億6千万円のいずれか高い方までは相続税がかかりません。
<要件>
- 被相続人と配偶者が法定婚にあること
- 申告期限までに相続税申告をすること
- 配偶者が被相続人から財産を取得すること
③未成年者の税額控除
未成年者が被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合に、未成年者の相続税額を一定額控除できる特例です。
控除額は、未成年者の年齢と相続税額に応じて、150万円~400万円です。
<要件>
- 相続人が未成年者であること(令和4年3月31日以前の相続または遺贈については「20歳」)
- 取得時に日本国内に住所がある人、または日本国内に住所がない人でも、次のいずれかの条件を満たす人
- 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人
- 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除く)
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
④相次相続控除
相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合に、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。
軽減額は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、今回の相続に係る相続税額から控除できます。
<要件>
- 被相続人の相続人であること(相続の放棄をした人および相続権を失った人を除く)
- その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
- その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
⑤住宅用不動産(空き家)に関連する譲渡所得の特別控除
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用財産(空き家)を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる特例です。
法改正により期間が令和5年12月31日→令和9年12月31日まで延長する予定です。(改正内容は令和6年1月1日以降の譲渡に適用)
この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
→国税庁ホームページ【No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】
<要件>
- 被相続人の居住の用に供されていた家屋であること
- 相続または遺贈により取得していること
- 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却していること
- 売却した家屋が次のいずれかに該当しないこと
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の老人ホーム等
- 相続開始の直前まで事業の用に供されていた家屋
- 相続開始の直前まで貸付けの用に供されていた家屋
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- 売却代金が1億円以下であること
上記に挙げた制度や特例は、ご家庭により利用可能かの判断基準が異なりますので、ご利用を検討する際には専門家へ相談する事をお勧めいたします。
(制度や特例の内容は2023年5月時点の情報を基にしています)
5.生前贈与と相続、どちらにしても正しい生前対策が重要

はじめにお伝えしたように、生前贈与と相続のどちらが有利か??についてはケースバイケースです。
とはいえ、ある程度の判断基準は下記のように示すことが出来ます。
実際にご家庭の財産額によってどういった対策を取るかについては、専門家に確認する必要があります。
①財産総額が相続時の基礎控除額以内で収まる場合
財産総額が相続時の基礎控除額以内で収まるのであれば、そもそも相続税申告をする必要がありませんので、相対的に相続の方が有利だと言えるでしょう。
②財産が金銭のみの場合
不動産がなく、金銭のみの場合、相続時に利用できる特例等は多くありません。
そのため、ご年齢にもよりますが、計画的に財産を渡せる状況であれば、生前贈与を活用していくと最終的に相続税の節税に繋がります。
ただし配偶者の方については、相続時の配偶者特例がありますので税金に限って言えば相続の方が有利と言えるでしょう。
③財産のほとんどが不動産の場合
②と対比して財産のほとんどが不動産の場合、贈与税や登録免許税、不動産取得税といった税率の観点のみを考えると、相続の方が有利と言えます。
また、配偶者の方が居住用の不動産を取得するのであれば、相続時の特例の利用も見込めます。
④不動産も金銭もある場合
この場合は判断が非常に難しく、ケースバイケースとなります。
どちらが有利、という事ではなく、『どちらも上手く活用していく』ことが得策と言えるでしょう。
生前贈与と相続、どちらにせよ明確にお伝えできることは、『ご家庭にあった生前対策をすることが何においても重要』という事です。
また節税対策だけでなく、認知症対策や相続トラブル回避等、目的に応じて適切な方法を選択し組み合わせていくことが重要です。
6.まとめ
生前贈与と相続は、財産の移転に関する2つの異なる制度であり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
節税対策や相続トラブル回避等、目的に応じて適切な方法を選択することが重要です。
今回のトピックスでは、生前贈与と相続の違い、それぞれのメリット・デメリット等を比較検討し解説しました。
財産の移転に関して悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
下記フォームよりお問合せ下さい。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
気軽にご相談ください。